
長野市長沼地区での復興まちづくり(休眠預金活用事業)
こんにちは!
今回はJPF加盟NGOであり、休眠預金活用事業「台風15号・19号被災地支援プログラム」の実行団体である「SEEDS Asia(以下SEEDS)」の活動内容などを紹介いたします。
SEEDSは2019年の台風19号で大きな被害を受けた長野市の長沼地区において、地域資源の再発掘による復興まちづくりを行っています。こちらはJPFの「令和元年台風被災者支援」プログラムにおける「Withコロナ時代の復興まちづくり協力事業」と併せた支援事業となります。
令和元年の台風19号以前より、高齢化の進んでいた長沼地区では、新型コロナウイルスの感染予防に、十分に配慮した復興のまちづくりや人材育成が必要とされてきました。そのため、コロナ禍でも住民の意見をしっかりと収集していくための工夫が求められます。しかしながら、まだまだIT化やデジタル化へのハードルは高いことから、子どもから高齢者まで、より簡単に意見を伝えられる、りんご形のカード「復興まちづくりんご」を作成しました。

今後も定期的に事業内容や現地の方の声などを紹介していきます。
台風15号・19号被災地支援プログラム|休眠預金等活用事業|国際協力NGOジャパン・プラットフォーム(JPF)
新型コロナウイルス対応緊急支援の採択団体のご紹介(休眠預金活用事業)
JPFは、休眠預金活用事業「新型コロナウイルス対応緊急支援」に関し、2つのプログラムにおいて、資金分配団体に指定されております。今回は、そのうちの一つである在留外国人支援に関し、採択団体と活動地域などをご紹介いたします。
★特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク
活動地域:全国
事業名:新型コロナ 移民・難民相談支援事業
★特定非営利活動法人 北関東医療相談会
活動地域:北関東
事業名:医療からほど遠い在留外国人の側に立つ
★公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 ※JPF加盟NGO
活動地域:東京都豊島区とその周辺
事業名:生活・法的支援による包括的生活安定支援
★特定非営利活動法人 青少年自立援助センター
活動地域:全国
事業名:外国人保護者と若者のための就労支援事業
★特定非営利活動法人 日越ともいき支援会
活動地域:全国
事業名:在留外国人コロナ緊急支援事業
★社会福祉法人 日本国際社会事業団
活動地域:北関東
事業名:移住者コミュニティのエンパワメント事業
★一般社団法人 反貧困ネットワーク
活動地域:関東
事業名:公的支援を利用できない外国人の相談・居住・医療支援事業
★公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター
活動地域:北海道
事業名:北海道在住外国人緊急支援プロジェクト
各団体の具体的な活動内容については、今後、紹介していきたいと思います!
休眠預金等活用事業|国際協力NGOジャパン・プラットフォーム(JPF)
(公社)シャンティ国際ボランティア会 アジアの子どもに教育を。本を通じて世界が拓ける|公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会(SVA)
公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター HIECC/ハイエック

災害支援事業の採択団体のご紹介(休眠預金活用事業)
JPFは休眠預金活用事業の2020年度の災害支援事業(防災・減災支援、緊急災害支援)の資金分配団体にも指定されております。今回は採択団体と事業内容について、簡単にご紹介いたします。
同事業では、ガバナンス・コンプライアンス体制、事業分野における経験、ネットワーク形成の実現可能性などに関する審査を経て、下記の団体を採択いたしました。
★特定非営利活動法人 ワンファミリー仙台/特定非営利活動法人 YNF ※2団体のコンソーシアム申請
活動地域:徳島県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県
事業名:防災・減災に取り組む民間団体等への災害ケースマネジメントノウハウ移転事業
★一般社団法人 ピースボート災害支援センター ※JPF加盟NGO
活動地域:岡山県、全国
事業名:避難所運営の人材育成と支援調整のための全国ネットワークの形成
★特定非営利活動法人 岡山NPOセンター
活動地域:岡山県、全国
事業名:支援団体の動きと被災地状況をリアルタイム共有する仕組みづくりプロジェクト
今後、各団体の具体的な活動内容についても、紹介していきたいと思います!
休眠預金等活用事業|国際協力NGOジャパン・プラットフォーム(JPF)
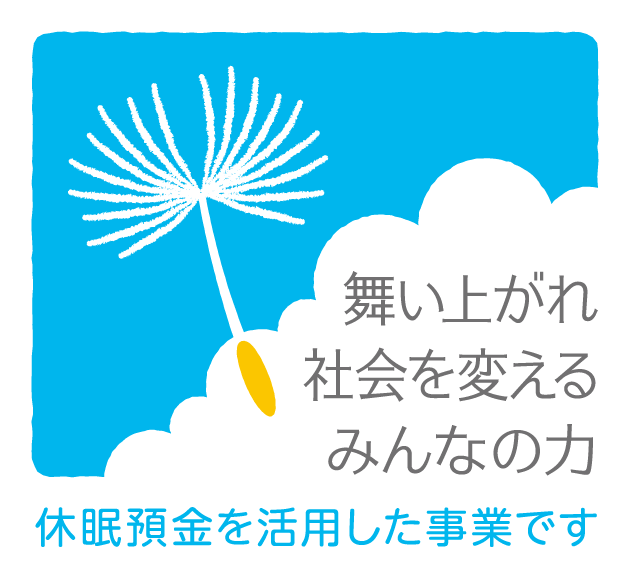
宮城県大郷町で住民の元気を支える取り組み(休眠預金活用事業)
今回は、「台風15号・19号被災地支援プログラム」の実行団体であり、JPF加盟NGOでもある「日本インターナショナル・サポート・プログラム(JISP)」の活動内容を紹介いたします。

JISPは、宮城県大郷町で令和元年台風19号被災者支援を実施しております。大郷町の仮設住民にはご高齢者が多く、洪水による被災に加え、新型コロナの影響もあいまって、外出や社会的交流、運動量が激減し、体力低下や体調不良、倦怠感、不安、意欲低下や孤独感等などの課題を抱えておられました。この問題に取り組むため、これまで日常的な営みとしていた農作業を通じて、被災者の元気を取り戻し、孤立を防ぐための活動を実施しています。
仮設住宅ではプランタや畑での農作業を支援しています。暑い夏の日も、ご自宅の玄関前でプランタの手入れに励む住民さんをよくお見かけします。プランタに植えた花や野菜が見事に成長し、時には住民同士でお花見したり、野菜を収穫している様子も見られ、手軽なプランタ栽培はご高齢の方に大好評です。仮設近隣に設置した「ハローガーデン」で、様々な野菜を栽培されているご高齢の参加者は、「沢山収穫できたら、仮設の隣近所に配りたい」と、日々畑仕事を楽しまれています。
また、台風被害の深刻であった、中粕川地区にもプランタ栽培支援を拡大し、土手先地区においては、公民館近隣の花壇への花植えの活動を行いました。多くの受益者から、「土弄りは夢中になれるし、心が落ち着く」と嬉しい声を頂いています。大郷の皆様の元気を支えるため、今後とも地域の方々と共にこの活動に取り組んでいきます。

▼日本インターナショナル・サポート・プログラム
▼JPF休眠預金活用事業「台風15号・19号被災地支援プログラム」https://www.japanplatform.org/contents/kyuminyokin/programs/reiwa-typhoon2019.html
長野市北部地域で子どもと保護者の支援(休眠預金活用事業)
こんにちは、JPF休眠預金活用事業担当です!
久しぶりの地域ブログ更新となりますが、今後は休眠預金事業を中心に活動内容などを紹介していきます。
今回は「台風15号・19号被災地支援プログラム」の実行団体である「NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト」の活動内容などを紹介いたします。

令和元年の台風19号で被災されたお子さんやその保護者の方々は、昨年からは新型コロナウイルス感染症の影響も加わって、まだまだ大変な日々を過ごしています。ながのこどもの城は、支援活動として「子どもの居場所の設置・運営」「リフレッシュプログラム」「保護者の居場所の設置・傾聴活動」を地域のボランティアとともに継続しています。支援プログラムを利用された保護者の方から、以下のようなメッセージをお寄せいただきました。
災害があり、コロナもありで、子どもたちもですが、私自身もいっぱいいっぱいになってしまうことがありますが、みなさんが快く子どもを預かってくれるのでとても助かります。お迎えに行った時など、少しお話させていただいたりしますが、私もすごくホッとした感じになれます。本当に感謝しています。
今後も定期的に活動の内容や現地の方の声などを紹介していきます。
▼NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト
▼JPF休眠預金活用事業「台風15号・19号被災地支援プログラム」
https://www.japanplatform.org/contents/kyuminyokin/programs/reiwa-typhoon2019.html
休眠預金担当のごあいさつ(休眠預金等活用事業)
この度、ジャパン・プラットフォーム(JPF)休眠預金事業担当となりました瀧田です。
JPFには2006年から2012年の6年間在籍し、5年ほどドイツで暮らした後、2017年に帰国、そしてJPFに戻ってきました。
コロナ禍により寄付の減少が見込まれる中、これまで社会課題に取り組んできたNGO・NPOの存続も危うくなってしまう可能性があります。NGO・NPOを支えるため、そして彼・彼女らが取り組んでいる課題解決をサポートするために、休眠預金を活用した助成というカタチで貢献していきたいと考えています。
先日パソコン内のデータの整理をしていたら、懐かしいものが出てきました。今から12年前の2008年、当時JPFをサポートしてくださっていた英会話学校のウェブサイトに寄稿した短い文章です。
**********************************
はじめまして。人道支援組織ジャパン・プラットフォームの瀧田真理と申します。
業務ではウェブ担当ではありますが、自分の文章を投稿することは滅多にないので、ちょっと緊張しています。
さて、みなさんは幼い頃、どのくらい親の仕事を理解していましたか?
私には6歳になる娘がいるのですが、彼女の理解力+想像力に驚かされることがありました。
(ひょっとして親バカなだけかも知れませんが・・・)
ある日、ミャンマーでサイクロンの被害にあった人々が取り上げられているテレビニュースを見ながら、
「ママはこの人たちを助けるお手伝いをしないといけないから、保育園のお迎えが遅くなっちゃうと思うの。ごめんね。」と伝えました。
すると娘は、自分の机にむかって何かごそごそしているなと思っていたら、小さな短冊を沢山もって私のところにやってきました。
その短冊1枚1枚には、それぞれ異なる色でハートが書いてあり、短い言葉が添えてありました。
「おうちがないひとへ」
「おかあさんがいないひとへ」
「ままがいなくて こどもがごはんつくるひとへ」
「こまた(困っている)ひとへ」

これらの短冊を、サイクロン被災者に渡して欲しいというのです。
「だって、きれいなハートが書いてあるカードをもらったら、嬉しい気持ちになるでしょ?きっと元気になると思うの。」
娘は母親がたずさわっている仕事を彼女なりに理解し、想いをカタチに表してくれたのでした。
私は、娘の他人を思いやることのできる優しさと成長に驚かされると同時に、日々の忙しさのなかで忘れがちなことを思い出させてもらいました。
寄付はたくさん集まるだろうか、書類はしっかり揃っているのか・・・。
これらのことは大切ではあるけれど、本来の目的ではなかったはず。
「こまたひと」が元気になれるために、また明日からがんばらなくっちゃと思うのでありました。
**********************************
毎年のように発生する自然災害、これまでに経験したことのない感染症蔓延下での支援活動。乗り越えるべき課題は少なくないですが、ひとりでも「こまたひと」に支援を届けることができるよう、休眠預金事業を通して尽力していきたいと思っています。